家の骨組みを作る建築と、その内側を彩るインテリアや家具。どちらが欠けても成り立たない両者の関係。では、建築家の目から“インテリア”はどのように見えているのでしょう? そんな疑問を投げかけるため訪れたのは、建築家・廣部剛司さんのお宅。居を構えるのは、周囲を家や公園に囲まれたいわゆる住宅街。しかしそこには、喧騒を忘れるほどに静謐な空気が広がっていました。17年前、8ヶ月に渡る海外放浪の末に作り上げた自邸に込めた思い、そして選び抜いた家具とは? 住まいのプロが築いたその空間には、自然界のなかで暮らすための心地よいリズムが流れていました。
 地球と繋がる家づくり
地球と繋がる家づくり
TAKESHI HIROBE(ARCHITECT) 場所:自宅
玄関の扉を開けるとまず目に飛び込んでくるのは、まっすぐに続く階段とその先の光。「この家を設計する時、階段部分は繰り返しスケッチを描いていましたね。求心的な空間、向かう先を必ず光にしたかったんです。毎日生まれ変わる、そんな気持ちを込めました」そう話す廣部さんの家には、至る所に窓が設けられているのも印象的です。「自然のなかで起きているアクションをそこにいるだけで感じられる、というのが1番のコンセプトなんです。この家を建てて17年になりますが、坪庭に植えたノムラモミジが色づいたり、階段の上の天窓に降り始めた雨音が響いたり、何度味わっても新鮮で感動します。自分の家でいろんなことを実験してみて、そのフィードバックを仕事に活かす。実際に自分が体感したことだから、施主さんにも説得力を持って勧められるんですよ。この家は、享受する空間であり、教師でもあると思っています」

日常の中に自然を取り入れる廣部さんのバランス感覚。それはどのように培われたものなのでしょうか?「独立する前に、8ヶ月間海外を廻っていろいろな国の建築を見た経験が大きいです。例えばアリゾナに行くと一軒見るために500キロ運転するなんてことがざらなんですよね。何もない砂漠の一本道をひたすら走りながら、ふと紫色の夕焼けに出合ったりして。そうするとあまりの美しさにやられちゃうんですよ。地球って素晴らしいなぁって。それ以来、もともと好きだった空や木をより意識して見るようになりましたね。建築でも、地球が持ってきてくれるいろいろな瞬間を感じ取りやすいようにしたいんです。だから施主さんに『この家に住んでいたら、いつの間にか月の方向を覚えちゃいました』なんて言われると、よしよしと思う(笑)意外と人間ってそういう自然のリズムのなかで癒されてリセットできるものなんです。特に居住空間はそうであるべきだと思いますね。家はできて終わりじゃないんですよ。住んでいく中で変わっていく余白の部分を楽しむのも醍醐味です。だから僕は設計に携わった家の家具選びにも立ち会うようにしてます。建築と家具、トータルで雰囲気を作り上げていくことが大切ですね」

廣部剛司さんのインテリアを構築する4つの要素

 GUITAR
GUITAR
 DINING TABLE
DINING TABLE


廣部さんの家にいると、時折ここが内側なのか外側なのかわからなくなる瞬間があります。そこには、都市住宅ならではの工夫が詰まっていました。「自然との調和を意識した開放感のある設計を心がけているのですが、ここの立地は、ぐるっと住宅に囲まれています。当然周りの目が気になりますので、プライバシーを守りつつも外とのつながりをいかに持たせるか、ということにこだわりました。閉塞感の出るカーテンは使わず、建物と道路の間にバッファー(距離)を取って坪庭を作り、その間に目隠しとなる植木を配置してみたり、自然光を取り入れる小窓を目線より高い位置に設けているのもそのためです。壁は内も外も左官塗りでひとつなぎに統一し、あえて窓枠を作らないことで境界を曖昧にしています。また、リビングとテラスをブリッジ(格子状の鉄柵を橋板として使用)で繋げて自由に行き来できるのもポイントです。そうすることで、本来外にあるテラスがまるで内側にあるかのように感じられる設計にしています。空間を積極的に区切らず、シームレスにする。それが開放感を生む秘訣なんです」。

- 廣部 剛司 TAKESHI HIROBE
-
廣部剛司建築研究所 代表取締役。一級建築士。
日本大学理工学部海洋建築工学科非常勤講師。
趣味は音楽と車。
著書に「サイドウェイ 建築への旅」(TOTO出版)
http://www.hirobe.net/
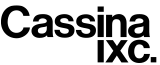






SOCIAL :